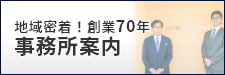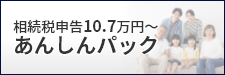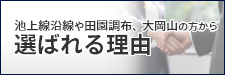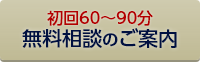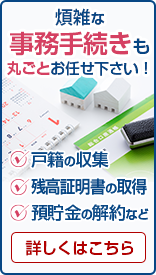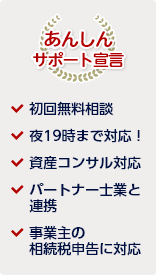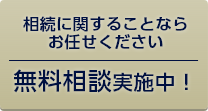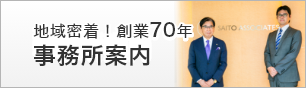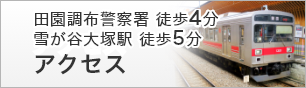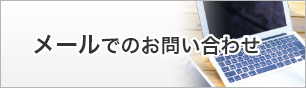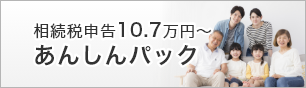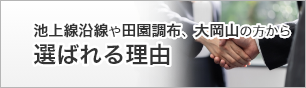相続税申告
2023年05月08日
Q:亡くなった父の自宅を相続しますが、相続税が納められるか心配です。なにか税金を軽減するための控除や特例がないか税理士の先生に話を聞きたいと思っています。(久が原)
久が原の自宅で同居していた母が亡くなり、相続人である妹と話し合った結果、久が原の実家を私が、母の預貯金を妹が相続することになりました。
問題は相続税申告についてです。東京都内である久が原の実家の評価額はそれなりの額になることが予想されます。今回の相続においても実家の価値の方が母の所有していた預貯金よりも高く、そのまま住み続けることを条件に妹に譲歩してもらいました。それゆえ、私自身は現金や預貯金といった遺産を相続できないため、相続税をきちんと納められるかが心配です。
独身でそれなりに自分でも貯金をしてきましたが、あまりに高額となると家を売却する方向で妹と遺産分割をやり直さなければなりません。
被相続人の自宅等を相続する際に使える控除や特例などを教えていただけますでしょうか。(久が原)
A:被相続人が住んでいた自宅を相続する場合であれば、相続税申告において「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいたり、事業用として使っていたりした土地を一定の要件を満たす親族が相続する場合、土地の評価額を減額できるという相続税の特例です。
今回のケースでは、被相続人が住んでいた自宅を同居していた親族である相続人のご相談者様が相続するということなので、下記の要件を両方満たせば、330㎡までは土地の評価額を80%減額することができます。
- 相続開始の直前から相続税申告の期限までその建物に居住し続けていること
- 対象の宅地等を相続開始時から相続税申告の期限まで保有していること
今回の相続においてご相談者様はご自宅を売るつもりがないとのことですので、上記の要件にあてはまる可能性が高いのではないでしょうか。(居住の要件を満たすことが前提です)
小規模宅地等の特例は、誰がどの土地を引き継ぐかによって要件が異なりますので、詳しい要件については雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。
相続税申告の実績多数の雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告のエキスパートである税理士が複雑な相続税申告も対応いたします。どんな些細な事でもご質問をお受けいたしますので、相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある久が原の方は、まずは初回無料のご相談をご活用ください。久が原の皆様の様々な事情をお伺いし、専門的なサポートを提案させていただきます。
2023年04月04日
Q:相続税について、配偶者が受けられる控除があると聞きました。これについて税理士の先生に詳しくお話を伺いたい。(久が原)
税理士の先生にお伺いしたいことがあり相談をさせていただきました。長く闘病を続けていた主人が、先月治療の甲斐なく亡くなりました。夫は小さいながらも自分で会社を経営しており、事務所は駐車場などの不動産が久が原に複数あります。相続税申告が必要になるであろうことは生前に主人とも話をしていましたが、実際この状況になってみてやらなければならない手続きが多くあり困っています。
一番の懸念は相続税の納税にあたり現金がありませんので、どう捻出をしようかと悩んでおります。知り合いには、配偶者の負担を減らす制度があったはずとのことでは話を聞いたのですが、この制度について税理士の先生に詳しくお話を伺えればと思います。(久が原)
A:相続税における配偶者控除を利用することで、相続税の税額軽減が可能になります。
お問い合わせいただきありがとうございます。雪谷・池上相続税申告相談室の社員一同、お手続き完了まで親身に対応をさせていただきます。
相続税申告において、配偶者には税額を軽減する制度(相続税の配偶者控除)がありますのでこちらを利用することで税額の軽減することが可能になります。
この相続税の配偶者控除とは、故人の配偶者が遺産分割及び遺贈により取得した遺産額が次記す金額のどちらか多い金額までは相続税の対象にはならないという制度です。
【相続税の配偶者控除】
上記の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能。
例として、ご相談者様が実際に取得した遺産総額が1億円の場合、上記1億6千万円に満たないため相続税の課税対象ではありません。注意が必要な点として、この相続税の配偶者控除を利用する場合は、もし事前に課税対象ではないと判断ができる状況であったとしても、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので納税は必要ありませんが、相続税申告は必ず行いましょう。
もし、遺産のほとんどが不動産であった場合、上記のように金額で単純に価値を表すことができません。ご自分の判断で1億円に見たないと思っていた不動産も、実際に専門家が正しい知識によって評価すると、その評価次第では1億円以上の評価額になるケースもございます。
また、相続税の申告納税は、「申告納税制度」を採用しています。これは納税者ご自身で計算をして算出することを意味します。この算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことにより最終的な納税額を抑えることが可能になるのです。
そのためには、相続税申告に関する知識と多くの実績が必要となります。相続税の申告納税について分からない点がある方は、相続税を専門とする税理士へ相談することをおすすめいたします。
相続税申告は申告と納税の期限というものが決まっています。ですからスピーディーに、かつ正確に手続きを行う必要があります。相続税申告の必要があるかどうか判断をするのは一般の方には難しい内容となりますから、まずは相続税を専門とする税理士へと相談をしましょう。雪谷・池上相続税申告相談室は久が原で相続税を専門とする税理士として多くの相談実績があります。久が原での相続税申告には自信がございますので、まずは当相談室の無料相談をご利用いただき現在のお困りごとをお聞かせください。久が原の皆様からのお問い合わせを所員一同でお待ちしております。
2023年03月09日
Q 税理士の先生教えてください。生前に贈与を受けていたのですが、この贈与分も相続税の対象になりますか?(久が原)
私は久が原に住む40代男性です。先日同じく久が原に住む父が亡くなりました。母は既に他界しておりますので、相続人は私と妹の2人だけです。相続税の節税対策として、私と私の息子は父から生前贈与を受けておりました。5年前から毎年贈与を受け取っておりましたが、1年あたりの贈与額は110万円未満でしたので、贈与税は納付していません。この相続分は、今回の父の相続においてどのような扱いになるのでしょうか。(久が原)
A 被相続人の死亡日からさかのぼって3年間の贈与分は相続税の計算に含まれます。
被相続人の亡くなった日からさかのぼって3年の間に受け取っていた贈与分については、相続税の計算に含まれます。その対象となるのは、今回の相続で財産を受け取った下記のような方々です。
- 受遺者
- 財産を取得した相続人
- 相続時精算課税制度の適用者
- 生命保険金などのみなし相続財産を取得した方
上記に該当する方が被相続人の存命中に贈与を受けていた場合、その贈与分を相続税の計算に含める必要があります。今回のケースに当てはめると、ご相談者様は相続人にあたりますので、お父様が亡くなる日より前の3年の間にご相談者様が受け取った贈与分については、課税価格に加算しなければなりません。
ご相談者様のご子息については、生命保険金などを受け取っているかによって扱いが異なってきます。
ただし贈与税には特例があり、課税価格への加算が不要となる可能性もありますので、お客様のケースが特例に適用されているかどうかよく確認する必要があります。
相続税の計算は、今回挙げたような制度を把握した上で行わなければならず、専門知識が求められます。
ご自身での判断が難しい場合はお早めに相続税の専門家である税理士に依頼することをおすすめいたします。なぜなら、計算を誤り本来の申告額よりも少ない納税額を申告してしまった場合や、計算に時間がかかり申告期限に間に合わなかった場合はペナルティを受けるとこになるからです。ご自身が不利益を被る事態に陥る前に、専門家に依頼するのは得策と言えるでしょう。
雪谷・池上相続税申告相談室では相続税に特化した専門知識を持つ税理士が、久が原にお住まいの皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
久が原にお住まいの皆様、ならびに久が原で相続税申告について相談できる事務所をお探しの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
まずはお気軽にお電話ください
0120-79-3704
営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応