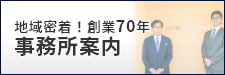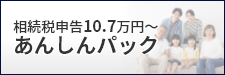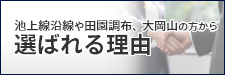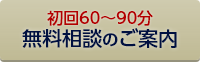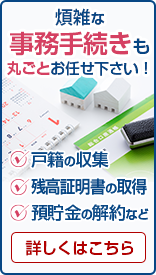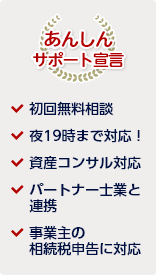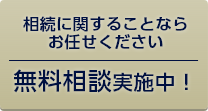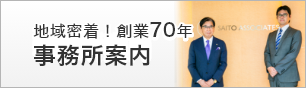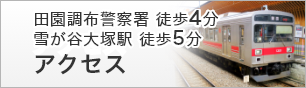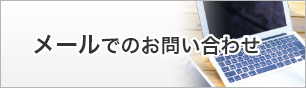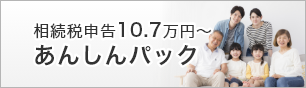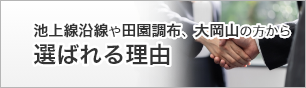相続税申告
2023年02月02日
Q:相続税申告が期限に間に合わなさそうです。税理士の先生どうしたら良いでしょうか(大岡山)
昨年父が亡くなり相続が発生しております。子である私と弟は大岡山には住んでいないのですが共に都内に住んでおります。
母も私たちも父が相続税申告が必要なほど財産が多いとは思っていなかったので、相続手続きは母に任せておりました。父と母は仲が良かったので母は父が亡くなって落ち込む期間もあり、やっと少しずつ遺品の整理を始めました。すると先日母から父が残していた通帳がいくつか見つかったとのことで連絡がありました。また、郊外に不動産も所有していたようです。所有していた不動産と預金を合計するともしかしたら相続税申告が必要になるのではないかと慌てた様子でした。
今更ながら相続税申告には期限があると知って困っております。税理士の先生、何とかならないでしょうか?(大岡山)
A:相続税申告の期限を延長することはできませんが、対応方法はございます。
相続税の申告および納税には期限が定められており、残念ながら原則期限を延ばすことはできません。申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内となっております。
期限延長が認められる場合もありますが、準備が間に合わない、遺産分割が整わないといった個人的な理由では認められておりません。
しかしながら相続税申告が期限内に間に合わない場合の対応方法はございますのでご安心ください。
申告する相続税額を算出するには遺産分割がまとまり、それぞれの相続人が相続する相続財産について決定している必要があります。したがって遺産分割がまとまっていない場合には相続税申告を行うことができないことになりますが、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法がございます。
この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行います。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が大岡山エリアの皆様の複雑な相続税申告をサポートしております。まずはご相談ください。
2023年01月06日
Q:父の相続発生時に死亡保険金を受け取りました。相続税の計算に影響するのか税理士の先生に教えてもらいたいです。(久が原)
相続税に関して質問があり、税理士の先生に問い合わせいたしました。
2か月前、久が原に住む私の母が亡くなり、相続税申告が必要になりました。地主の娘であった母は祖父の相続の際に久が原近辺の土地をいくつか相続していたようです。自分の死後に相続税申告を行わなければならないことを知っていたようで、相続税対策のひとつとして生命保険に加入していました。受取人は相続人である私と弟、妹の3人で、死亡保険金の額は合計して3,000万円ほどになります。どうやら母が10年前に受け取った退職金を元手に生命保険をかけていたようです。
手続きも無事にすみ、兄弟それぞれが1000万円ずつ受け取りましたが、問題は相続税申告です。
そもそも遺産総額より相続税申告が必要なことは分かっていましたが、死亡保険金をどのように扱ってよいのかわかりません。3,000万円と高額なため、税額に大きく影響するのではないかと心配しています。
税理士の先生に相続税申告における死亡保険金のあつかいについて教えてもらえないでしょうか。なお相続人は保険金を受け取った3人のみです。(久が原)
A:死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、非課税限度額が設定されています。
雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続において死亡保険金が関係する際には、はじめに契約内容を確認してください。相続税の対象となるのは、被相続人が契約者として保険金を支払っていた場合です。契約内容によっては贈与税や所得税等の対象になります。
そもそも相続における死亡保険金は受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の必要はありませんが、相続税の計算を行う際には「みなし相続財産」として課税対象です。
【保険の契約内容と税金の関係】
・契約者…夫(被相続人) 被保険者…夫(被相続人) 受取人…妻や子→相続税
・契約者…夫 被保険者…妻(被相続人) 受取人…夫→所得税・住民税
・契約者…夫 被保険者…妻(被相続人) 受取人…子供→贈与税
今回の場合、お母様が契約者および被保険者、受取人がご相談者様とご兄弟に指定されていたとのことなので、相続税の課税対象となるパターンにあてはまるでしょう。
お母様が相続税対策として死亡保険金をかけていたのは、死亡保険金には非課税限度額が設けており、同額の現金を遺産として相続するよりも、課税価格を下げられるからです。死亡保険金の非課税限度額は下記の式に当てはめて計算します。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回のケースでは法定相続人が3人ということなので、1500万円が非課税限度額になります。
1500万円を超える分にたいして税金が課されるので、3000万円-1500万円=1500万円が課税対象です。なお、この制度の対象は相続人に限定されるため、相続人以外が保険金を受け取った際には適用されません。
相続に死亡保険金が関係するケースでは相続税の計算が複雑になるため、ぜひとも専門家である税理士にご相談ください。
雪谷・池上相続税申告相談室は、久が原エリアおよび久が原周辺の皆様の相続税申告をサポートいたします。雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原の皆様の相続税申告について、地域事情に精通した税理士が親身にご対応いたします。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご活用いただき、皆様のお悩みをご相談ください。久が原ならびに久が原周辺で相続税申告にお悩みの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年12月02日
Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告にあたって、父の自宅にあった現金はどう扱ったらよいでしょうか。(田園調布)
先日、田園調布の実家に住む父が亡くなり、私と母で実家の遺品整理をしています。相続をする際はまず遺言書の有無を確認するようにと知人から聞いていたので、書斎から探し始めました。すると、引き出しの奥から紙袋に入った大量の紙幣、いわゆる“たんす預金”が出てきました。母が言うには家にあった現金は相続税の申告とは関係ないのではないかとのことですが、実際にはどうしたらよいのでしょうか。現在のところ相続税の申告が必要かどうかまだはっきりとはわかりませんが、もしこの現金が相続税の対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。(田園調布)
A:たんす預金も含めて、被相続人の方が保有していた財産は、全て相続税の課税対象となります。
相続税の申告は“申告納税制度”といって、相続人ご自身で遺産を確認して、相続税の対象かどうかの確認を行い、相続税額を計算して申告納税しなければなりません。たんす預金も含めて、手もとにある現金はすべて相続税の課税対象となります。財産調査がまだ済んでいないようでしたら今後も現金が出てくる可能性があります。それらすべて相続税の申告対象となりますので、全財産を集計する必要があります。たんす預金は、銀行のように明確な金額を証明することが出来ません。したがって、相続人が遺品整理で見つけた現金のみについて集計し、相続財産として申告します。
なお、“申告納税制度”だからといって、申告対象として計算せず、ご自宅に保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座などを調査し、口座残高に動きがあった場合や不穏な動きがあった場合、さらに死亡前後の現金の引き出しについても調査されます。調査があった場合、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不自然な動きがなかったか確認され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指しており、田園調布周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。雪谷・池上相続税申告相談室には田園調布の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、田園調布の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご説明いたします。初回のご相談は無料ですので、田園調布の皆様、ならびに田園調布で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。
まずはお気軽にお電話ください
0120-79-3704
営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応